-

スハ32 地方普通列車セット
¥16,500
本キットからは、Wルーフのスハ32(スハ32600)が登場した昭和初期の普通列車のうち、福島~仙台や福知山~米子など、地方の普通列車をイメージした編成を作ることができます。また、名古屋周辺などの都市内短距離列車にも最適です。さらにスハ32やナハ22000といった三等車を増結する、スニ30やオニ26600といった荷物車を追加することでより実感的な編成が再現できます。 本キットには、スニ30(狭窓or広窓ランダム)*1、スロハ30*1、スハ32*2、スハフ32*1が含まれます。車体、屋根、床板、台枠表現、TR13/23台車、ベンチレーター、等級帯デカール、蓄電池箱、幌パーツがセットに含まれています。車輪と連結器、白文字表記類は別途ご準備ください。
MORE -

スハ32 近郊普通列車セット
¥16,500
本キットからは、Wルーフのスハ32(スハ32600)が登場した昭和初期の普通列車のうち、東京~熱海や大阪~神戸など、短距離の普通列車をイメージした編成を作ることができます。さらにスハ32やナハ22000といった三等車を増結する、スニ30やオニ26600といった荷物車を追加することでより実感的な編成が再現できます。 本キットには、スニ30(狭窓or広窓ランダム)*1、スロ33*1、スハ32*2、スハフ32*1が含まれます。車体、屋根、床板、台枠表現、TR13/23台車、ベンチレーター、等級帯デカール、蓄電池箱、幌パーツがセットに含まれています。車輪と連結器、白文字表記類は別途ご準備ください。
MORE -

スハ32 幹線普通列車セット
¥16,500
本キットからは、Wルーフのスハ32(スハ32600)が登場した昭和初期の普通列車のうち、東京~神戸や上野~青森など、長距離の普通列車をイメージした編成を作ることができます。さらにスハ32やナハ22000といった三等車を増結する、スニ30やオニ26600といった荷物車を追加することでより実感的な編成が再現できます。 本キットには、スニ30(狭窓or広窓ランダム)*1、スロ32*1、スハ32*2、スハフ32*1が含まれます。車体、屋根、床板、台枠表現、TR13/23台車、ベンチレーター、等級帯デカール、蓄電池箱、幌パーツがセットに含まれています。車輪と連結器、白文字表記類は別途ご準備ください。
MORE -

マイロネフ37(マイロネフ37280)
¥2,500
本キットはマロネフ37280由来のマイロネフ37のキットです。 ベンチレーター、台車、床下機器類(大型蓄電池など)、幌枠、インレタは別売です。
MORE -

急行17・18列車(名士列車)~昭和初期の姿~
¥36,300
急行17・18列車は、東京~神戸を結んでいた急行列車です。起源は明治39年に設定された新橋~神戸を夜行で結ぶ1/2等急行3・4列車とされますが、設定当初から名門列車と位置付けられていました。17・18列車も政財界の要人など、多くの知名の士が利用し、「名士列車」と呼ばれていました。 本セットでは、昭和初期の鋼製客車が活躍していた時代の急行17・18列車を再現できます。本キットには、車体、屋根、床板、台枠表現、TR13/23/71/73台車、ベンチレーター、等級帯デカール、蓄電池箱、幌パーツが含まれます。車輪と連結器、白文字表記類は別途ご準備ください。
MORE -

マロネフ37(マロネフ37550)
¥2,500
本キットはマロネフ37550由来のマロネフ37のキットです。 ベンチレーター、台車、床下機器類(大型蓄電池など)、幌枠、インレタは別売です。
MORE -
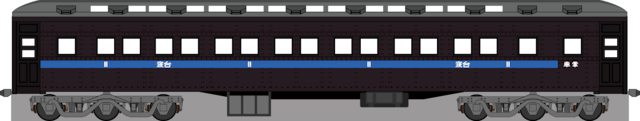
マロネフ37(マロネフ37500)
¥2,500
本キットはマロネフ37500由来のマロネフ37のキットです。 ベンチレーター、台車、床下機器類(大型蓄電池など)、幌枠、インレタは別売です。
MORE -

マロネ37(マロネ37350)
¥2,500
本キットはマロネ37350由来のマロネ37のキットです。 ベンチレーター、台車、床下機器類(大型蓄電池など)、幌枠、インレタは別売です。
MORE -

マロネ37(マロネ37300)
¥2,500
本キットはマロネ37300由来のマロネ37のキットです。 ベンチレーター、台車、床下機器類(大型蓄電池など)、幌枠、インレタは別売です。
MORE -

マイネフ38(マイネフ37230)
¥2,500
本キットはマイネフ37230由来のマイネフ38のキットです。 ベンチレーター、台車、床下機器類(大型蓄電池など)、幌枠、インレタは別売です。
MORE -

マイネ38(マイネ37130)
¥2,500
SOLD OUT
本キットはマイネ37130由来のマイネ38のキットです。 ベンチレーター、台車、床下機器類(大型蓄電池など)、幌枠、インレタは別売です。
MORE -

マイネフ37(マイネフ37200)
¥2,500
本キットはマイネフ37200由来のマイネフ37のキットです。 ベンチレーター、台車、床下機器類(大型蓄電池など)、幌枠、インレタは別売です。
MORE -

マイネ37(マイネ37100)
¥2,500
本キットはマイネ37100由来のマイネ37のキットです。 ベンチレーター、台車、床下機器類(大型蓄電池など)、幌枠、インレタは別売です。
MORE -

スイテ38(スイテ37000)
¥2,500
本キットはスイテ37000由来のスイテ38のキットです。 ベンチレーター、台車、床下機器類(大型蓄電池など)、幌枠、インレタは別売です。
MORE -

特急「富士」列車~昭和初期の姿~
¥36,300
特別急行「富士」は明治45年に新橋~下関間に運転を開始しました。それ以来、1・2列車は豪華な設備を備え、客層も富裕層や貴族、要人に限られていました。 本セットでは、昭和初期の鋼製客車が活躍していた時代の特急「富士」列車を再現できます。本キットには、車体、屋根、床板、台枠表現、TR13/23/71/73台車、ベンチレーター、等級帯デカール、蓄電池箱、幌パーツが含まれます。車輪と連結器、白文字表記類は別途ご準備ください。
MORE -

オハ31 荷物列車セット
¥16,500
本キットには17m級鋼製客車オハ31系列の客車のうち、郵便車スユ30、郵便荷物車スユニ30、荷物車スニ30×3が含まれます。本セットは、大正中期~昭和初期の荷物列車をイメージしたセットです。スニ30は狭窓タイプと広窓タイプの車がランダムに含まれます。 オプションから、スユニ30をスユ30またはスニ30に変更することが可能です。 本キットには、車体、屋根、床板、台枠表現、TR11/13台車、ベンチレーター、蓄電池箱、幌パーツ、等級帯デカール、が含まれます。車輪と連結器、白文字表記類は別途ご準備ください。
MORE -

オハ31 普通列車増結セット
¥16,500
本キットには17m級鋼製客車オハ31系列の客車のうち、三等車オハ31×3、三等緩急車オハフ30×2が含まれます。本セットは、大正中期~昭和初期の普通列車の増結編成をイメージしたセットです。 本キットには、車体、屋根、床板、台枠表現、TR11/13台車、ベンチレーター、蓄電池箱、幌パーツ、等級帯デカール、が含まれます。車輪と連結器、白文字表記類は別途ご準備ください。
MORE -

オハ31 地方普通列車セット
¥16,500
本キットには17m級鋼製客車オハ31系列の客車のうち、郵便荷物車スユニ30、二三等車オロハ30、三等車オハ31×2、三等緩急車オハフ30が含まれます。本セットは、大正中期~昭和初期の地方線区の普通列車をイメージしたセットです。なお、スユニ30は両開き扉車です。 本キットには、車体、屋根、床板、台枠表現、TR11/13台車、ベンチレーター、蓄電池箱、幌パーツ、等級帯デカール、が含まれます。車輪と連結器、白文字表記類は別途ご準備ください。
MORE -

オハ31 幹線普通列車セット
¥16,500
本キットには17m級鋼製客車オハ31系列の客車のうち、荷物車スニ30、二等車オロ31、三等車オハ31×2、三等緩急車オハフ30が含まれます。本セットは、大正中期~昭和初期の幹線の普通列車をイメージしたセットです。 本キットには、車体、屋根、床板、台枠表現、TR11/13台車、ベンチレーター、蓄電池箱、幌パーツ、等級帯デカール、が含まれます。車輪と連結器、白文字表記類は別途ご準備ください。
MORE -

スユニ30(スユ36200)
¥2,500
本キットはスユニ36200由来のスユニ30のキットです。台車と床下機器、ガラベン、表記インレタ、及び近代化改造部品は別売です。 スユニ30は17m級鋼製郵便荷物車です。昭和2年にスユニ476000として15両が登場。昭和3年にはスユニ36200に称号を変更し、5両が増備。昭和16年にはスユニ30に称号を変更しました。郵便室側の引戸は当初、郵便受渡機取付用の引戸が装備されていましたが、後に両開き扉に改造されたようです。 戦前は全国の急行列車や普通列車で郵便荷物車の主力として活躍しました。戦災で1両が廃車され、戦後は普通列車を中心に活躍していたようです。例外的に特急"つばめ"の青大将色への徒食変更時期にスハニ35の代用として用いられたこともあったようです。その後、一部は救援車スエ30に改造されるも、それ以外は昭和42年までに全車が廃車されました。
MORE -

スユ30(スユ36000)
¥2,500
本キットはスユ36000由来のスユ30のキットです。台車と床下機器、ガラベン、表記インレタ、及び近代化改造部品は別売です。 スユ30は昭和2年にスユフ47500として30両が登場した17m級鋼製郵便車です。昭和3年にはスユ36000に称号を変更し、。昭和16年にはスユ30に称号を変更しました。車内設備として、従来郵便区分棚は車内内側にレール方向、外周部に枕木方向に配置されていたのを外周部にレール方向に配置されるようになり、これはのちの郵便車に受け継がれました。戦前の鋼製郵便車としては最多数を誇ったこともあり、郵便車の主力として急行列車などで活躍しました。 戦災で2両が廃車(その中の一部は70系客車に再利用)され、1両が接収されました。接収された車は途中で荷物車に改造され、スニ30に編入。昭和26,27年には2両がスユニ30に編入されました。これらは外観はほぼ変化がなかったようですが、郵便受渡機取付用の引戸は両引戸に改造されたようです。戦後は普通列車や荷物列車の他、一部の急行列車でも活躍。その後は半数以上がが配給車のオル31や救援車のスエ30に改造されました。その後は荷物車などへの転用改造もなく、昭和41年に消滅しました。また、松川事件の事故当該編成にも組み込まれており、2022年大学入学共通テスト日本史Bの写真を飾りました。
MORE -

オハフ30(オハフ34000)
¥2,500
本キットはオハフ34000由来のオハフ30のキットです。台車と床下機器、ガラベン、表記インレタ、及び近代化改造部品は別売となります。 オハフ30は昭和2-4年にオハフ34000として165両が登場し、昭和16年にはオハフ30に称号を変更しました。側板が鋼製となった以外は大型木製客車の最終増備型と大差ない形態で、車内も木製三等車と変わりませんでした。当初は真空制動屋根水槽式でしたが、すぐに空気制動床下水槽式に改造。ただし、水槽は魚腹台枠の中央株に取り付けられたため薄い形態だったようです。 戦前は特急列車にこそ使用されなかったものの、全国の急行列車の主力客車として活躍。しかし20m級のスハ32600(スハ32)やスハフ34200(スハフ32)が増備されるにつれ、次第に普通列車に活躍の場を移していったようです。戦時中には、一部が通勤型に改造され、オハフ40に。戦災で8両が廃車(その中の一部は70系客車に再利用)。戦後は普通列車を中心に活躍していました。また、昭和34年以降、一部はオル30、オヤ30といった事業用車に改造されました。オハフ30自体も昭和30年後半から41年までに廃車され、姿を消しました。
MORE -

オハ31(オハ32000)
¥2,500
本キットはオハ32000由来のオハ31のキットです。台車と床下機器、ガラベン、表記インレタ、及び近代化改造部品は別売となります。 オハ31は昭和2-4年にオハ32000として512両が登場し、昭和16年にはオハ31に称号を変更しました。側板が鋼製となった以外は大型木製客車の最終増備型と大差ない形態で、車内も木製三等車と変わりませんでした。当初は真空制動屋根水槽式でしたが、すぐに空気制動床下水槽式に改造。ただし、水槽は魚腹台枠の中央株に取り付けられたため薄い形態だったようです。 戦前は特急列車にこそ使用されなかったものの、全国の急行列車の主力客車として活躍。しかし20m級のスハ32600(スハ32)やスハフ34200(スハフ32)が増備されるにつれ、次第に普通列車に活躍の場を移していったようです。戦時中には、一部が通勤型に改造され、オハ41に。戦災で44両が廃車(その中の一部は70系客車に再利用)。戦後は普通列車を中心に活躍していました。また、昭和31年以降、一部はオル31、オヤ27、オヤ30、スエ30といった事業用車に改造されました。オハ31自体も昭和30年後半から41年までに廃車され、姿を消しました。
MORE -

オロハ30(オロハ31300)
¥2,500
本キットはオロハ31300由来のオロハ30のキットです。台車と床下機器、ガラベン、表記インレタ、及び近代化改造部品は別売となります。 オロハ30は昭和3-4年にオロハ42350として48両が登場。昭和3年にはオロハ31300に称号を変更し、。昭和16年にはオロハ30に称号を変更しました。中央にトイレを備え、その前後に二等客室と三等客室を備えていました。二等室部は近距離用として向かい合わせ固定式座席を装備し、2枚1組の窓配置でした。三等室部はオハ31に準じたボックスシートを装備し、3枚1組の窓配置でした。 戦前は主に地方線区の急行列車や普通列車で活躍していたようです。戦災で3両が廃車(その中の一部は70系客車に再利用)。その後も普通列車を中心に活躍していました。オハ35とオハフ33で挟まれ、C56で牽引された3両編成の準急"ちどり"などが有名です。昭和35年から廃車が始まり、オハ26への格下げ改造もされ、オロハ30としては昭和36年に形式消滅。オハ26に格下げされた車も昭和41年までに消滅しました。
MORE